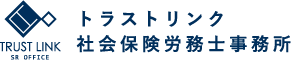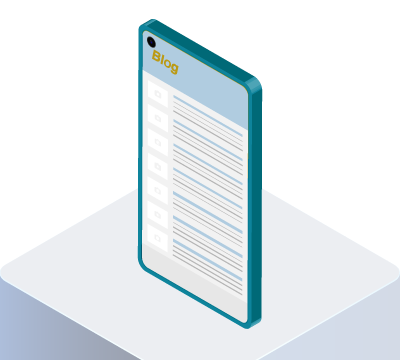Ⅰ 出生後休業支援給付金(夫婦ともに会社員で雇用保険加入者の場合の妻の会社における手続き、添付資料について)
出生後休業支援給付金の手続きにあたって、必要となる添付書類を教えてください。
妻が「出生後休業支援給付金」支給申請を行う場合には、特殊な場合を除き、確認書類として住民票(世帯全員、続柄あり)の添付が必須となります。それ以外にも、育児休業給付金の支給申請では必要なかった書類が状況に応じて必要となっています。
また、夫が「出生時育児休業給付金」と同時申請せず、「出生後休業支援給付金」のみで支給申請を行う場合には、住民票(世帯全員、続柄あり)の添付が必要です。

妻の出生後休業支援給付金の申請手続きについてはレポート前号でも触れましたが、特殊なケースを除いては、住民票の添付が必須であることが分かりました。
そこで、今回は、夫婦ともに会社員で雇用保険加入者のケースにおける、妻の会社の「出生後休業支援給付金」手続き、添付資料について訂正を加え、解説いたします。
1.配偶者(夫)が出生後育児休業給付金を受給している場合
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」の「28.配偶者の被保険者番号」欄に夫の雇用保険被保険者番号を記入し、下記のすべてを添付します。
- 妻の賃金台帳・出勤簿
- 母子健康手帳の写し(ない場合は医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)等)
- 住民票(世帯全員について記載されたもの、続柄あり)
2.配偶者(夫)が休業中も給与支給され出生後育児休業給付金を受給していない場合
(1)配偶者(夫)が出生後育児休業給付金支給申請をして不支給決定を受けている場合
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」の「31.配偶者の状態」欄に「7」と記入し、下記のすべてを添付します。
- 妻の賃金台帳・出勤簿
- 母子健康手帳の写し(ない場合は医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)等)
- 住民票(世帯全員について記載されたもの、続柄あり)
- 「配偶者が育児休業をすることができないことの申告書」→⑨にチェック、その右欄に夫の雇用保険被保険者番号を記入する
- レポート前号で『「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」の「配偶者の被保険者番号」欄に夫の雇用保険被保険者番号を記入して提出』と記載しましたがこれは誤りで、上記が正しい内容です。
(2)配偶者(夫)が出生後育児休業給付金支給申請をしていない場合
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」の「31.配偶者の状態」欄に「7」と記入し、下記のすべてを添付します。
- 妻の賃金台帳・出勤簿
- 母子健康手帳の写し(ない場合は医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)等)
- 住民票(世帯全員について記載されたもの、続柄あり)
- 「配偶者が育児休業をすることができないことの申告書」→⑨にチェック
- 夫の「育児休業証明書」→夫の会社の証明が必要
- 夫の「育児休業申出書」→夫が夫の会社に提出したもの
「配偶者が育児休業をすることができないことの申告書」と「育児休業証明書」は、厚生労働省のホームページに書式がございますので、そちらをご使用ください。「育児休業証明書」については、書類名が類似の「育児休業証明」がございますので、お間違いのないようご注意ください。
3.留意点
以上については現時点でハローワークにも確認を重ねた内容です。記載方法、添付書類等については不明瞭なことも多く、今後も修正、変更の可能性があります。実務にあたっては適宜確認の上、手続きください。
Ⅱ 高年齢者雇用の更新基準等について
今年3月末をもって、労使協定で定年後再雇用の対象者基準を定める経過措置が終了になりますが、今年4月1日以降、再雇用契約を更新する基準に同様の基準を定めることは可能でしょうか。
また、業務があれば65歳以降も継続雇用することも考えていますが、その場合の留意点も教えて下さい。
定年後再雇用者の更新基準を設ける場合は、退職事由・解雇事由に該当する場合にとどめておいた方がよいと考えます。
65歳以降の継続雇用については、定年後再雇用者の場合は第二種計画の申請、認定を受けておくべきです。その他は解説をご確認下さい。
1.60歳から65歳までの高年齢者雇用確保措置
65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置(①定年の引上げ、②継続雇用制度、または③定年の定めの廃止)を講じなければなりません。多くの企業で、60歳定年後、有期契約で再雇用し、65歳まで更新する継続制度が設けられています。
また、2013年4月1日より高年齢者雇用安定法が改正され、労使協定により継続雇用制度対象者を限定する仕組みが廃止、本年3月末には一部適用できていた対象者を限定する経過措置も終了します。
以上から、本年4月以降は希望者全員が継続雇用の対象となります。ただし、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができるとされています(平成24年厚生労働省告示560号)。
2.65歳から70歳までの高齢者就業確保措置の努力義務化
2021年4月1日からは、65歳から70歳までの就業機会を確保することが、企業の努力義務となりました(法的義務はありません)。定年廃止、定年延長、継続雇用制度の導入といった高年齢者雇用確保措置と同様の措置に加えて、特殊関係事業主以外の企業への再就職に関する制度、フリーランスや起業による就業に関する制度、社会貢献活動への従事に関する制度等のうち、いずれかの措置を講ずることが事業主の努力義務となります。
65歳以降の高年齢者については、体力や健康状態その他本人を取り巻く状況がより多様なものとなることから、対象者を限定する基準を設けることは可能とされています。ただし、対象者基準を設ける場合には、事業主と過半数代表者等との間で十分に協議した上で、過半数代表者等の同意を得ることが望ましく、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められないとされています。恣意的とならないよう、対象者基準は具体的、客観的な基準を設けておくことが重要です。
3.65歳までの定年後再雇用者の更新基準の設定について
定年後再雇用者を、契約期間満了を理由に更新せずに契約を終了(雇止め)できるかについては、労働契約法19条により判断されます。
同法は、①契約が反覆更新され期間の定めのない雇用契約だと社会通念上同視できる場合(第1号)、及び、②更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合(第2号)は、更新拒絶に客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当であると認められなければ雇止めできないと定めています。雇止めが有効か無効かについては、無期契約の解雇よりは緩やかに判断され得るとの解釈もありますが、実際の裁判では雇止めが無効となるケースが多く、慎重な対応が必要です。そして、定年後再雇用者については、上記①のケースは多くなく、②の適否で判断されることになります。
②の適否については、定年後再雇用者の場合、高年齢者の65歳までの継続雇用の提供という高年齢者雇用安定法の趣旨からすると、雇用継続の期待利益は特段の事情がない限り肯定されると解されます。つまり、雇用継続の合理的期待がある中で、客観的合理的な事由と社会通念上の相当性があるかどうかで判断されることになります。
高年齢者雇用安定法の趣旨からは、再雇用の対象者選定と同様、心身の故障や著しい能力不足・勤務状況不良を更新基準と定め、それを理由として雇止めを行うことが妨げられるわけではありません。しかし、雇止めを行った個別的事情から「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないもの」かどうかで、有効か無効か判断されます。
例えば、テヅカ事件(福岡地判令2.3.19労判1230-87)は、60歳で定年退職後に継続雇用され2回の契約更新を経た65歳未満の労働者について、業績悪化に伴う雇止めが問題となった事例で裁判所はこれを無効としています。また、ヤマサン事件(富山地決令2.11.27労判1236-5)は譴責の懲戒処分を受けたことを理由に始期付き嘱託再雇用契約が解除された事例で、譴責処分を受けたことは解雇・退職事由に該当するといえないとし、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当とは認められないことから、解除は無効であると判断されました。
このように定年後再雇用者については、雇用継続の合理的期待があるとされる可能性が高く、雇止めの状況の客観的合理的理由と社会通念上の相当性の適否が問題となってくるため、退職事由・解雇事由以外で設けた更新基準を適用して契約終了するには、相当慎重な対応が必要になります。また、更新基準自体を再雇用基準より厳しく規定することは、高年齢者雇用安定法の趣旨に反して合理性が否定されるものと解するとの説もあります(有斐閣「労働契約法第2版」土田道夫648頁)。以上から、定年後再雇用者の更新基準を設ける場合は、退職事由・解雇事由に該当する場合にとどめておいた方がよいと考えます。
4.65歳以上の再雇用契約の更新基準の設定について
65歳以上の再雇用の場合には、上記2のように継続雇用の法的義務は無く、対象者基準を設けることも可能とされています。従って、雇用継続の合理的期待があるとされるか否かについては、どのような更新基準を設け適用したのか等、個別の事情によることになると考えます。上述のように、再雇用基準を恣意的に排除するようなものではなく、具体的、客観的基準で定め、それを更新基準にも適用するような立付けにしておくことが適切と考えます。
損害保険料率算出機構事件(東京地判平30.7.18LLI/DB判例秘書搭載)は、65歳年度末に定年退職後、1年間の有期労働契約で再雇用された再雇用者について、有期労働契約を更新しなかった事例で、雇止めが有効とされました。裁判所は、65歳定年者の6割程度の受け皿となるような制度にし、希望者全員を再雇用することは難しく、選抜が必要であると述べていたこと、再雇用条件及び更新条件は会社の業務上の必要性を一つの判断要素とし、再雇用条件と更新条件を区別する仕組みになっていないこと、さらに雇用契約書等に雇用延長を希望しても採用されない場合があることが明記されていることから、雇用継続の期待が無いと判断されました。
5.65歳以降も継続雇用する場合の留意点(第二種計画等)
(1)定年後再雇用者の場合
有期労働契約は通算5年を超えて更新された場合に、無期転換申込権が発生します。これまでの定年後再雇用制度は、60歳定年後、65歳までの再雇用上限を定めている企業が多く、この場合通算5年を超えないので無期転換申込権は発生しませんでした。
ところが最近、人手不足や70歳までの継続雇用が努力義務化されたこともあり、65歳を過ぎても業務があれば継続雇用しようという企業が増えてきています。この場合は有期契約が通算5年を超え、無期転換権が発生する可能性が出てきます。これに備えて、いわゆる「第二種計画」(高年齢者の雇用管理に関する計画)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けておけば、定年に達した後引き続いて雇用される間は無期転換権が発生しません。それほど複雑な手続きではないので、定年後再雇用者については当該手続きを行うことをお勧めします。
加えて、どのような人を65歳以降も継続雇用するのか、具体的、客観的な対象者基準を設けておき、更新基準も同様にしておくことが重要です。併せて、更新上限も定めておきます。
(2)定年を経ていない有期契約者の場合
60歳前から有期契約を更新し、60歳以降もずっと更新されている有期の契約社員やパートの場合は、要注意です。定年とは、労働者が一定の年齢に達した時に労働契約が終了することを言い、無期雇用者に適用される制度です。「第二種計画」は、「定年に達した後、引き続いて雇用される」場合が対象です。ずっと有期の場合は、定年を経ていないので「第二種計画」の対象外となります。また、他社(一定のグループ会社等を除く)を定年退職した人を有期で採用する場合も、定年後同じ事業主に引き続いて雇用されることになりませんので、「第二種計画」の対象外となります。
この場合、高年齢者の無期転換が想定されますので、第二定年を定めておくことが適切です。例えば、第二定年は70歳としたり、現状70歳以降も継続雇用しているような企業では、第二定年を75歳、もっと長ければ80歳といった設定をすることまで考えられます。
一方で、実際には無期転換権を行使しないケースも多いと思われますので、有期契約の更新上限(回数や年齢)を定めておくことが必要です。さらに、高齢のため健康状態の悪化や能力の低下で継続雇用が難しくなることも想定されます。雇用契約の締結、更新の時には、更新期限を超える更新を期待させるような言動を行わないことや、1年毎に達成すべき業務量や目標をできるだけ具体的に定めた更新基準を設け、基準に到達しない場合は更新を行わないといった運用を行うべきでしょう。